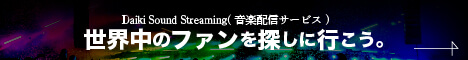SNS運用とは?始め方や運用代行の依頼タイミングも解説!
SNS運用は、企業がSNSを活用して「認知拡大」「集客」「信頼構築」などを図る重要なマーケティング手法です。
しかし、「どこからはじめればいいの?」「投稿するだけで効果はあるの?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事ではSNS運用の基本から、企業が取り組むべき理由、メリット・デメリット、運用前に決めるべきポイントまでを網羅的に解説します。
目次
- SNS運用とは?
- SNS運用が重要な理由
- SNS運用のメリット
- SNS運用の注意点
- SNS運用をはじめる前に決めるべきこと
- SNS運用を代行するかどうかの判断基準
- 迷ったら、プロの力も。SNS運用を成功につなげよう
- SNS運用代行に関する申し込み・お問い合わせ
SNS運用とは?

SNS運用とは、企業がX(旧Twitter)やInstagramなどのSNSアカウントを活用して、情報発信や顧客とのコミュニケーションを行い、ブランド認知や集客、信頼構築を図るマーケティング活動のことです。
SNS運用は単なる投稿業務ではなく、目的の明確化・戦略設計・コンテンツ制作・効果測定までを含む、継続的な運用を行うことが重要です。
SNSが情報収集の主要手段となった今、SNS運用は企業活動において欠かせない取り組みのひとつです。
SNS運用が重要な理由

テレビや紙媒体に代わり、SNSは情報発信の中心になりつつあります。ここでは、なぜ企業にとってSNSが不可欠なのかを解説します。
情報発信の主戦場がテレビからSNSへ移行している
総務省の「主なメディアの利用時間と行為者率」によると、2020年にはインターネット利用時間がテレビ視聴時間を上回りました。 このデータは、ユーザーの接触メディアが「テレビ中心」から「インターネット中心」へと移行したことを示しています。
なかでもSNSは、スマホと相性がよく、通勤や休憩などスキマ時間に閲覧される場として定着しています。今後、企業の情報発信手段としてSNSはテレビ以上に重要な位置を占めるといえるでしょう。
30代以下を中心にSNSが日常的な接触メディアとなっている
特に若年層では、SNSは日常的なメディアとして定着しています。総務省の「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によると、20代の「ソーシャルメディアを見る・書く」平均時間は、平日でも1時間を超えることがわかっています。
情報収集や友人とのやりとりだけでなく、商品・サービスへの関心喚起や意思決定にもSNSが影響を与える時代です。若年層との接点を築くうえで、SNSはもはや欠かせないチャネルといえるでしょう。
商品やサービスの検索行動がSNS中心に変化している
以前はGoogleやYahoo!などの検索エンジンが情報収集の主流でしたが、今はSNSで検索するユーザーが増えています。
Instagramのハッシュタグ検索や、Xでの口コミ調査など、SNSを検索ツールとして活用する行動は、特に若い世代を中心に一般化しています。企業はSNS上でも適切に情報を発信しないと、検索経由の流入を取りこぼすリスクがあるでしょう。
精度の高いターゲティング広告で効率的にアプローチできる
SNS広告は、ユーザーの年齢・性別・興味関心などをもとに、ターゲットを細かく絞り込んで配信できます。
従来のマス広告に比べて無駄なコストが少なく、自社の商材に関心を持つ層へピンポイントでアプローチできます。特にニッチな市場や特定属性のユーザーにリーチしたい企業にとって、SNSは極めて有効な広告媒体といえるでしょう。
SNS運用のメリット

SNS運用には費用対効果の高さや、ユーザーとの距離を縮められるといった利点があります。具体的なメリットをみていきましょう。
コストを抑えて認知拡大が狙える
SNSは基本的に無料ではじめられ、大きな広告費をかけずに情報発信が可能です。うまく活用すれば、広告よりも高いリーチやエンゲージメントを生むことも珍しくありません。
特に中小企業やベンチャー企業にとっては、限られた予算のなかでブランド認知を高める有力な選択肢です。投稿の質や運用体制を工夫することで、大手と同等の影響力を獲得することも可能です。
ユーザーと直接コミュニケーションが取れる
SNSは一方的な発信だけでなく、コメント・DM・いいねなどを通じて双方向のやりとりができます。ユーザーの声をリアルタイムで受け取り、すぐに反応できる点は大きな強みです。
たとえば、質問に即答したり、クレーム対応を迅速に行うことで、企業への信頼感を醸成できます。丁寧な対応が「ファン化」につながる可能性もあり、顧客ロイヤルティの向上に貢献します。
情報発信・ブランディングに活用できる
SNSは企業の世界観や価値観を日常的に発信できるメディアです。商品やサービスの紹介に加え、社員の働き方や企業文化、ビジョンなども発信可能です。
このような情報を継続的に発信することで、ブランドイメージがユーザーに浸透しやすくなります。広告では伝えきれない空気感やストーリーを届ける手段として、SNSは非常に有効です。
SNS運用の注意点

SNSは効果的な一方で、慎重な運用が求められる側面もあります。ここでは、導入前に知っておきたい主な注意点を紹介します。
炎上リスクと対応負荷がある
SNSでは、不適切な投稿や表現が「炎上」につながるリスクがあります。炎上が起きると、企業の信用失墜や売上への影響が避けられない場合もあります。
さらに、炎上時には迅速な対応が求められるため、社内体制やルールづくりが欠かせません。複数人での投稿チェックや、万が一に備えた対応マニュアルを準備しておくことが重要です。
成果が出るまでに時間がかかる
SNS運用は「すぐに結果が出る施策」ではありません。フォロワーの獲得やエンゲージメントの向上には、一定期間の継続的な取り組みが必要です。
日々の投稿や分析・改善を積み重ねることで、徐々に信頼やブランド力が構築されていきます。短期的な効果を期待するより、長期的な視点で運用に取り組むことが求められます。
継続的な運用体制が求められる
SNSは一度始めたら止めづらい施策です。投稿を継続しなければ、ユーザーの関心が薄れ、アカウントの信頼性が損なわれてしまいます。
そのため、計画的な投稿スケジュールの管理や、専任担当者の配置が重要です。社内に十分なリソースがない場合は、外部の支援サービスを検討することも選択肢となるでしょう。
SNS運用をはじめる前に決めるべきこと

成果を出すSNS運用には、事前の準備が不可欠です。ここからは、方向性を明確にし、効率的に運用をスタートさせるためのポイントを解説します。
目的を明確にする
SNS運用の出発点は「目的の明確化」です。認知拡大、集客、顧客との関係構築、ブランディングなど、目的によって投稿内容も運用方針も大きく変わります。
目的が曖昧なまま運用をはじめると、投稿の一貫性がなくなり、効果測定も困難になります。まずは「SNSを通じて何を達成したいのか」を、チーム全体で共通認識として明確にしておきましょう。
ターゲットを定める
誰に向けて情報を届けるのかを定めることも非常に重要です。ターゲットが不明確なままでは、投稿内容がぼやけ、刺さりにくくなってしまいます。
年齢・性別・職業・趣味などをもとに「ペルソナ」を設計し、その人物像に合わせた投稿を心がけましょう。ペルソナが明確になることで、訴求力のあるコンテンツが作りやすくなり、反応率も高まります。
SNS媒体を選ぶ
SNSと一口に言っても、X(旧Twitter)・Instagram・TikTok・Facebookなど、特性はさまざまです。たとえば、若年層向けならTikTokやInstagram、ビジネス層向けならXやLinkedInが適しています。
ペルソナとの親和性を考慮し、自社に最も合ったSNSを選定することが、無駄のない運用につながります。複数媒体を運用する場合も、役割分担を意識しましょう。
投稿方針とトンマナを設計する
投稿内容のジャンルや頻度、トンマナ(トーン&マナー)もあらかじめ設計しておくことが重要です。トンマナがブレると、ユーザーからの信頼感や統一感が損なわれてしまいます。
「カジュアル」「誠実」「ユーモラス」など、企業イメージに合った文体・ビジュアルを定め、すべての投稿で一貫性を持たせましょう。投稿フォーマットや文体ルールを明文化しておくと、複数人で運用する際にも効果的です。
社内での運用ルール・体制を整備する
SNS運用は、継続的なタスク管理とリスク対応が求められます。そのため、運用を担当するメンバーの明確化や投稿フロー、承認プロセスなどを事前に整えておく必要があります。
特に炎上リスクに備えた「投稿前チェック体制」や「緊急時の対応ルール」は必須です。属人化を避けるためにも、体制図や運用マニュアルを用意しておくと、安定的で安全な運用につながります。
SNS運用を代行するかどうかの判断基準
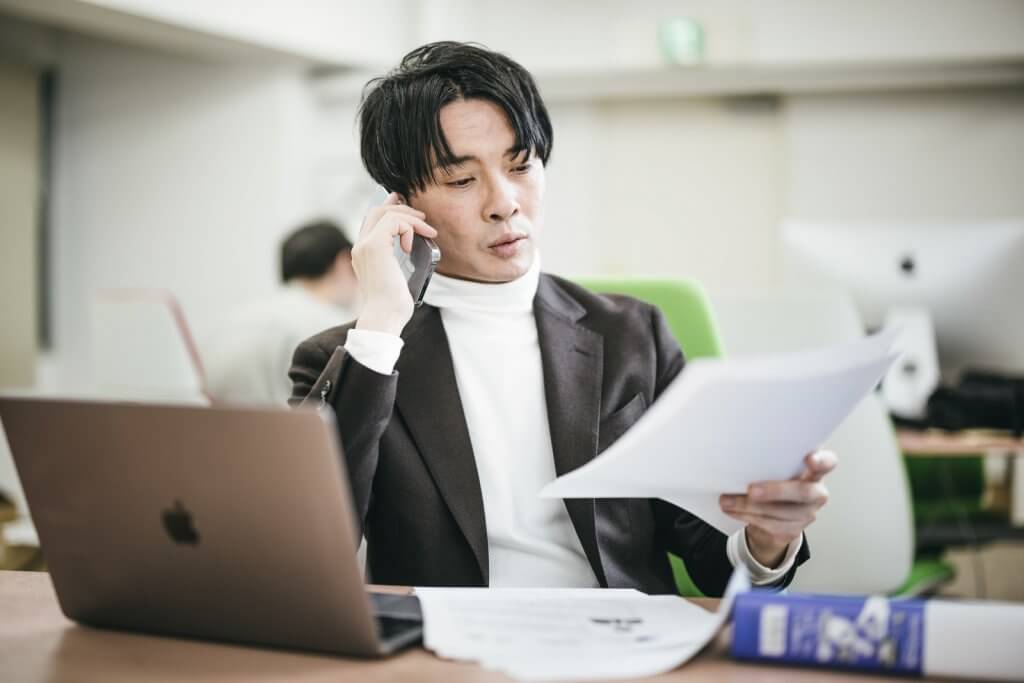
自社でSNSを運用すべきか、外部に代行を依頼すべきかは慎重な判断が必要です。以下の6つの観点から検討してみましょう。
社内にリソース(人手・時間)が足りているか
SNS運用は、投稿作成・スケジュール管理・分析・改善など、想像以上に多くの業務が発生します。もし本業と兼務で時間を割けない、担当者がいないという状況であれば、運用が後回しになりがちです。
投稿頻度が不安定になれば成果にもつながりにくく、逆効果になることもあります。限られたリソースのなかで質の高い運用が難しい場合は、代行を検討するタイミングといえるでしょう。
社内にSNSマーケティングの知見があるか
SNSは使うだけなら簡単ですが、「運用」となると話は別です。アルゴリズムやトレンド、ユーザー心理を踏まえた戦略設計が求められます。
もし社内にそのノウハウがない、学ぶ時間が取れないという場合は、経験豊富なプロに依頼することで、戦略的なアプローチが可能になります。知見の有無は成果に直結するため、重要な判断ポイントです。
成果に対する明確な目標やKPIがあるか
「とりあえずはじめたSNS」では成果が見えづらく、方向性も定まりません。フォロワー数・クリック率・コンバージョン数など、目標やKPIが明確であることが重要です。
社内で設定が難しい場合や、設定しても分析や改善が追いつかない場合は、プロのサポートを受けることで、数値をもとにした効果的な運用が実現できます。目標設定の段階で迷いがある場合も、代行は有効といえるでしょう。
投稿コンテンツの質や企画力に課題があるか
SNSでは、ただ情報を発信するだけでなく、目に留まりやすく、共感されるコンテンツが求められます。企画力やデザイン、文章のクオリティが不足していると、ユーザーの反応は鈍くなりがちです。
「何を投稿すればよいかわからない」「投稿がマンネリ化している」と感じるなら、プロによる企画・制作の代行が効果的です。質の高いコンテンツを安定供給できる体制が構築できます。
SNSからの集客や売上に課題を感じているか
SNSを運用しているものの「フォロワーは増えたが集客にはつながっていない」と感じる企業も多いはずです。
原因としては、ユーザーの導線設計が不十分であったり、発信内容と商品・サービスとの接点が曖昧であったりする可能性があります。
売上につながるSNS活用ができていないと感じたら、外部の視点で改善策を講じることが、課題解決への近道となるでしょう。
外注にかけられる予算が確保できているか
SNS運用代行はコストが発生するため、予算の確保は大前提です。ただし、自社で非効率な運用を続けることによる「見えない損失」も無視できません。
外注費用と社内負担、得られる効果のバランスを比較し、投資対効果をシミュレーションすることが重要です。一定の成果を出したい場合は、予算を確保してプロのサポートを得ることも十分に検討すべき選択肢です。
迷ったら、プロの力も。SNS運用を成功につなげよう
SNSは、ただの情報発信ツールではありません。企業やアーティストがファンと出会い、関係を深め、ブランドを育てるための「体験の場」です。だからこそ、適切な戦略と継続的な運用が求められます。
本記事では、SNS運用の基本・重要性から、メリット・デメリット、代行の判断基準まで解説してきました。SNS運用は、正しく設計し実行できれば、確かな成果につながるマーケティング手法です。
とはいえ、実際の運用には企画・撮影・編集・投稿・分析と多くの工程が発生します。忙しい現場でこれらをすべて担うのは、簡単ではありません。そこで活用いただきたいのが、ダイキサウンドのSNS運用代行サービスです。
【ダイキサウンドのSNS運用代行サービス】
- 台本作成から動画編集・分析まで、SNS運用のすべてを代行
- TikTokフォロワー5万人超のZ世代クリエイターによる刺さる動画制作
- 投稿後のインサイト分析や改善提案まで含む継続サポート
お客様のブランドや世界観に寄り添いながら、SNSで「バズらせる仕組み」を弊社が作ります。「何からはじめればいいかわからない」「続けられるか不安」そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。